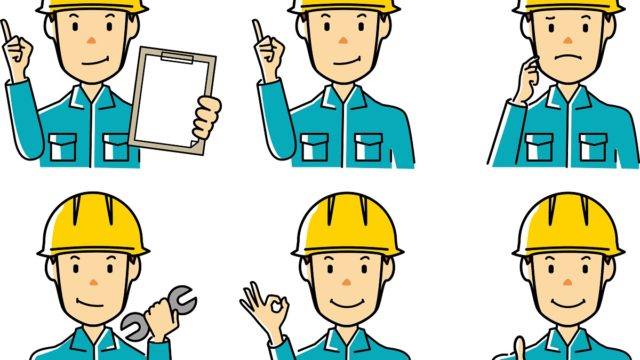今年の2月に二次試験を合格し、実務補習を3月と7月、そして9月の3回に分けて実施しました。
そうです、合計15日間の実務補習を無事に終えることができました。
3月は、製造業。
7月は、サービス業。
9月は、建設業。
診断士協会により、業種を偏りなく差配してくれました。
3回とも、メンバーに恵まれ、非常に楽しく取り組むことができました。
強いて言えば、3月が少し大変でした。
初めての経験だったこと、さらには、経営戦略(リーダー)を買って出たこともあって、全員の報告書に目を通したり、方向性を決めたりと、結構負荷が高かったように思います。
7月は、プロモーションを担当し、9月は財務を担当しましたが、班員でしたのでそれ程負荷は高くありませんでした。
この実務補習は、二次試験に合格してから診断士登録を行うまでしか経験することができない制度なので、もう一度経験することができません。
今思うと、実務補習を経験してよかったと感じています。
その理由は、たくさんの同期診断士や指導員に出会えたためです。
同期診断士は、5名✕3回=15名と関わることができましたし、
指導員も5名(7月と9月の実務補習では、副指導員がおられました)に出会えたことにまります。
とくに、同期診断士は、一流メーカーの方だったり、公認会計士、税理士、銀行員、コンサルタント等々、いろんな職業の方がおられましたが、皆さん優秀な方が多いと感じました。
さすがに難関試験を突破してこられた方は違うなあと感心することが多々ありました。
中小企業診断士として登録するには、二次試験に合格した後、3年以内に以下のどちらかの要件を満たす必要があります。
- 実務補習を15日以上受ける
- 診断実務に15日以上従事する(実務従事)
HiroPaPaの場合は、前述のとおり、実務補習を選択しました。
二次試験合格後すぐに、診断実務に携わることは難しいと思いますので、ほとんどの方は実務補習を選択することになるかと思います。
実務補習は、中小企業診断士協会が主催するものなのですが、民間が主催するものもあります。
実は、民間主催の実務補習の方が拘束時間が短かったり、費用が安かったりします。
3月に実務補習をご一緒された方の中には、民間の実務補習に切り替える方もいらっしゃいました。
HiroPaPaが中小企業診断士協会主催の実務補習を選択した理由は、二つあります。
一つ目は、診断士のつながる機会を増やしたかったからです。
実務補習の機会は、二次試験合格直後の今しか経験できませんし、同期の診断士に数多く出会える機会だと考えました。
二つ目は、本業の会社で実務補習の費用を負担してもらえるため、コスト負担が少なかったからです。
これは本当に助かりました。実務補習では1回につき約6万円かかりますので、合計18万円の費用負担になります。
一時的に建て替える必要がありますが、最終的には返金され、個人負担が不要になるというのは大きいです。
そんなこんなで、本日、診断士登録の申し込みを行いました。
申し込みに必要な書類は、次の4つです。
- 中小企業診断士登録申請書
- 中小企業診断士第二次試験合格証書
- 実務補習修了証書(15日分以上)
- 住民票
診断士の免許が届くのを楽しみに待つとしましょう!
あと、気になるのが官報への掲載と、中小企業診断士のバッジの入手方法です・
官報への掲載は、中小企業庁のホームページへの掲載でも可と見直し(令和4年から)になったようで、官報掲載が無くなったのなら、ちょっと残念です。
バッジの方は、都道府県の協会に入会すると入手可能で、購入ではなく貸与だとのこと。
東京は有償(3,000円)で、大阪は無償のようで、協会によって違うみたいです。
羅針盤をモチーフにしたこのバッジ。
HiroPaPaはかっこいいと思います。
欲しいですね。

でわでわ。