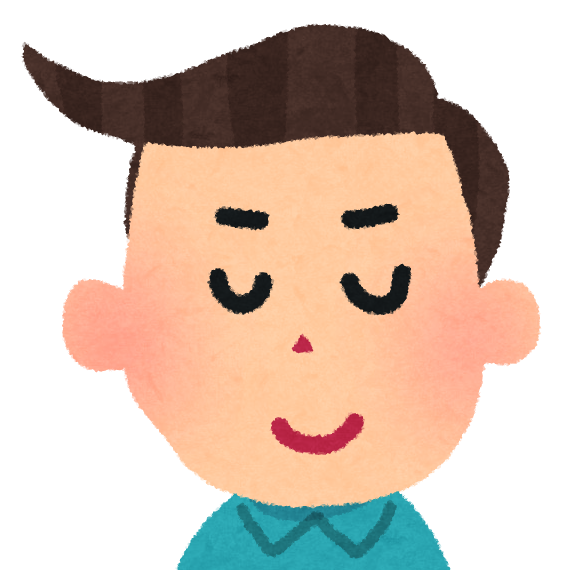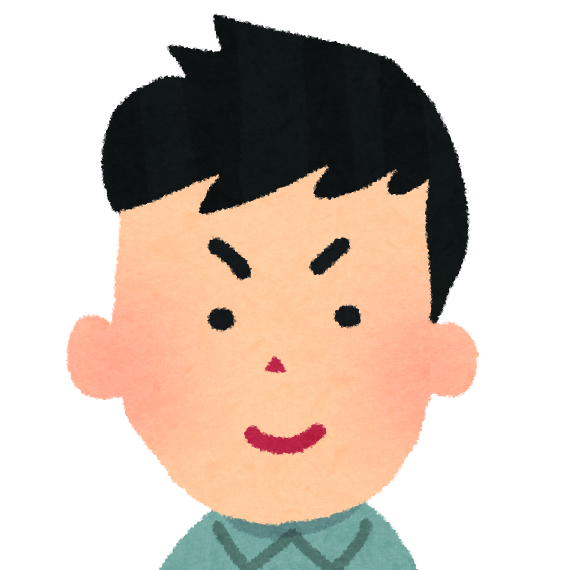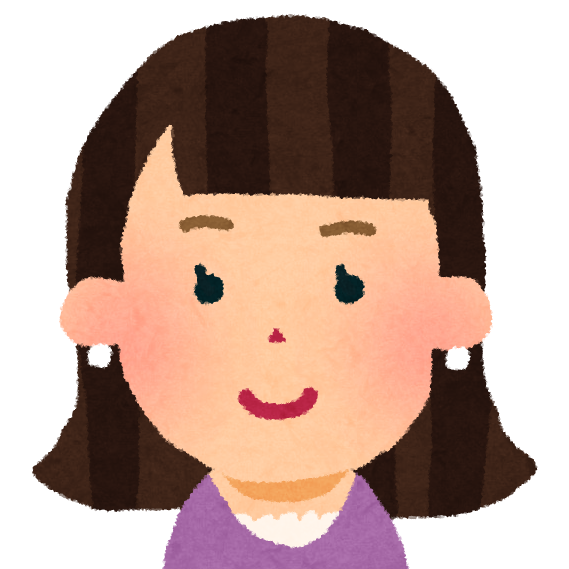こんなシーンですよね。上記のとおり、HiroPaPaは、まったくわかってませんでした。
なので、ここでも、ざっくりと整理しておきました。
目次
保育認定とは?認定はどこでもらうの?
幼稚園や保育園、認定こども園などを利用したい場合に必要な認定のことを保育認定といいます。
認定は住んでいる市町村でもらう必要があり、認定の種類により、利用できる施設が異なります。
つまり、
1号認定がないと、幼稚園や認定こども園に入れません。
2号、3号認定がないと、保育園や認定こども園に入れません。
ってことです。
幼稚園、保育園、認定こども園の違いについては、こちらを参考にしてください。

1号認定、2号認定、3号認定って何がちがうの?
もう、上述しちゃいましたが、認定区分によって、入れる施設が違ってきます。
1号、2号、3号のどれになるかってのは、親の働き方と働いている時間できまります。
といっても、自治体のホームページ見るのも面倒でしょうから、問診して差し上げましょう
※この就労時間は自治体によって違ってきますので、正確には各自治体のホームページで調べてくださいね。1ヶ月あたり48~64時間の範囲で、市町村が定めることとなります。
ちなみに、2号と3号の違いは、子どもの年齢です。
子どもの年齢が0歳~3歳の場合、3号の認定区分となり、
子どもの年齢が満3歳~5歳の場合、2号の認定区分となります。
認定の違いによる影響ってなんですか?
希望施設への申込み手続きが違ってきます
1号認定の場合(幼稚園、認定こども園)
- 幼稚園などの施設に直接申し込みを行います。
- 施設から入園の内定を受けます。(※ 定員超過の場合などには面接などの選考あり)
- 施設を通じて市町村に認定を申請します。
- 施設を通じて市町村から認定証が交付されます。
- 施設と契約をします。
2号認定の場合(保育園、認定こども園)
- 市町村に直接認定を申請します。
- 市町村が「保育の必要性」を認めた場合、認定証が交付されます。
- 市町村に保育所などの利用希望の申し込みをします。(希望する施設名などを記載)
- 申請者の希望、保育所などの状況に応じ、保育の必要性の程度を踏まえ、市町村が利用調整をします。
- 利用先の決定後、契約となります。
施設の利用料金が違ってきます
ここは10月に無償化制度が始まりますので、詳細は自治体のホームページで確認ください。
ただ、ざっくり言えば、2,3号認定もらえないと、そもそも希望の施設に入れなかったり、費用が割高になるってことですね。
まとめ
共働き家庭(ひとり親家庭含む)なら、2号(3号)認定を受けましょう。
見学などを行い、希望の施設を決めてから、住んでいる自治体へ申請申し込みを行うという順番になります。
自治体の方で点数化されており、就労時間や同居人、施設の受け入れ人数によって、認定されるかどうかがきまりまるのです。